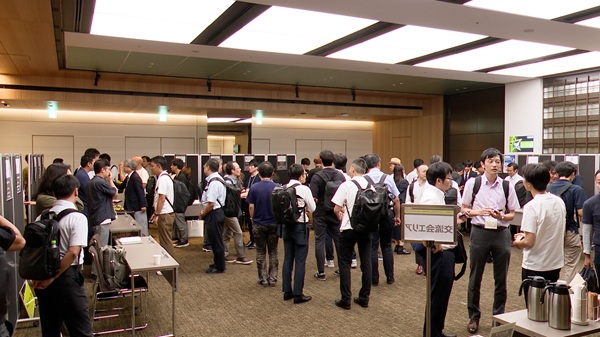2025.09.30
イベントレポート
アクセラレーションプログラム FASTAR 11th DemoDay(後編)
「FASTAR」とは、独立行政法人 中小企業基盤整備機構が実施するアクセラレーションプログラムです。
> FASTAR 11th DEMODAY イベントレポート【前編】はこちら8 株式会社ベホマル
代表取締役 西原麻友子氏

CO₂を吸収する世界初のプラスチック「DACプラ」
西原氏は、冒頭「私たちは身の回りのプラスチックを、二酸化炭素を吸収するプラスチックに変える、世界初の環境素材を開発している」と宣言。社会課題となっている地球温暖化への革新的なアプローチを提示しました。同社の独自技術「DACプラ」は、大気中のCO₂を自発的に吸収するプラスチックで、大きな設備投資を必要とせず、既存の製造ラインにそのまま導入できる点が特徴。既存のバイオマスプラスチックと異なり、成形性や外観を損なうことなく製品化できるため、幅広い分野への展開が可能だと強調しました。社会実装に向けた資金調達・企業連携、量産体制の確立と国際展開を見据えています。
審査員の荒木氏(ロート製薬)から「環境分野は欧州主導でルール形成が進む。国内だけでなくEUからの展開を検討しているか」と質問があり、西原氏は「すでに欧州の自動車メーカーや日本法人を持つ欧州企業と話を進めており、海外市場を重視している」と回答しました。
9 株式会社TAK(タック)薄膜デバイス研究所
代表取締役社長 藤井隆満氏
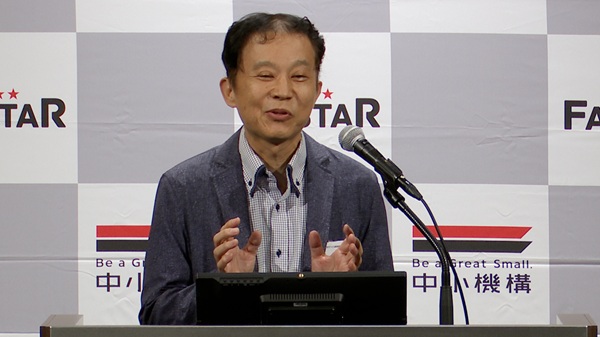
酸化ガリウム新構造「ε(イプシロン)型」で次世代パワー半導体に挑む
酸化物薄膜の研究開発を30年以上手がけてきた藤井氏が設立。前職で高性能圧電膜を開発し、米国で量産化に成功するなどの実績(特許出願200件超)を有し、日本発の半導体材料開発に挑戦。ピッチでは、同社が注力する次世代パワー半導体材料「酸化ガリウム」の新しい結晶構造であるε型を紹介。従来のα型やβ型と比べ、耐熱性・基板依存性に課題がある中、ε型は六方晶構造を持ち、安価なサファイア基板の利用が可能。さらにガリウム(GaN)との親和性が高く、大面積化・低コスト化に優れる点を強調しました。
審査員の手塚氏(三井住友銀行)から膜加工の仕組みや事業フェーズ、資金調達方針に関する質問がありました。藤井氏は「装置メーカーと協力し液体スパッタ法による膜形成を進めており、今後は材料メーカーやデバイスメーカーと連携してデバイス応用へ展開したい」と回答。資金用途としては専用装置や簡易クリーンルーム整備が当面の課題であり、大規模な投資が必要となるパワー半導体開発は共同開発・ライセンス型で臨む意向を示しました。
10 cycaltrust(サイカルトラスト)株式会社
代表取締役 須江剛氏

模造品被害75兆円市場に挑む、特許技術で真正性を証明
製品やソフトウェアの真正性を保証し、サプライチェーンの透明性を確保する鑑定証明システムを開発するスタートアップです。模造品による被害は世界で年間約75兆円、日本国内でも4.3兆円に達し、品質低下や安全リスクに直結しています。こうした課題に対し、同社は特許技術「マルチシグ認証」とブロックチェーンを組み合わせ、調達から廃棄までトレーサビリティを担保する仕組みを提供します。ピッチでは、まずは1社単位で導入できるサービスから市場参入し、将来的にはサプライチェーン全体を対象としたBtoBプラットフォームへ発展させる方針を説明。さらに消費者向けには、購入商品のICチップを専用アプリで読み取ることで、その場で真贋判定が可能な仕組みを紹介しました。
審査員の小池氏(THE CREATIVE FUND)から「国内での展開イメージ」について聞かれると、百貨店が二次流通まで追跡したいニーズに応える点を強調。さらに「アート市場で広がりにくい背景」については、「NFTの流行り廃りと異なり、当社は実物とデジタルを組み合わせた真正性証明に注力しており、著名ブランドや作品への導入を契機に普及を狙う」と述べました。
11 株式会社X(エックス)
代表取締役 米倉暁氏

繰り返し説明業務をなくすAI動画生成サービス「ライトビデオ」
「繰り返し説明業務をなくし、人間が人間らしい仕事に集中できる社会」を目指すスタートアップ。医療現場を例に、200床規模病院で看護師が行う入院案内・手術前後説明などの繰り返し説明が年間10万回規模に上る点を指摘。現場の課題を解決する「ライトビデオ」を開発しました。資料やテキストをアップロードするだけで、AIが自動で解析・構成し、最短5分で動画を生成します。編集は直感的で、レイアウト選択や翻訳、チャットボット埋め込みなども可能。更新内容は即時反映され、URLやQRコードを通じて共有できるため、常に最新の情報を届けられる点が特徴です。金融業界でもアフラックと説明自動化の取り組みを開始。米倉氏は「業界ごとに深掘りせず、汎用的な仕組みとしてグローバル展開する」と強調しました。
審査員の浅田氏(One Capital)から「テキストから動画を作る発想は面白い」と評価。ピボットの経緯や業界選定について質問には、「もともとはメタバース領域での活用を模索していたが、医療現場などより汎用的に価値を発揮できる方向へ転換した」と説明。今後は特定領域に深く入り込みすぎず、グローバル展開を視野に汎用的なプラットフォームを目指す姿勢を強調しました。
12 株式会社KeyWeave(キーウィーブ)
代表取締役 Co-CEO 畠山雄樹氏

ネット世代の感性をデータ化──SNSマーケティングを革新するウィーブ
縦型ショート動画を軸にしたSNS運用支援事業を展開するスタートアップです。登壇では「1億円の資金調達」と「事業加速に向けたパートナー探し」を目的に、自社の強みと今後の戦略を発表しました。同社は、幼少期からスマホやSNSに親しみ、多様な価値観と社会課題への関心を併せ持つ「Z世代」をターゲットに事業を展開。従来のマーケティング手法では響かない世代に対し、TikTokやInstagramを中心に縦型ショート動画を活用した双方向型の運用を支援。撮影・編集・投稿・分析をワンストップで提供し、短期間かつ業界標準コストで高品質なコンテンツを制作できる点が特徴です。今後の差別化戦略として、SNS上の動画を収集・分類し、AIによって自動的に複数の企画を生成する「企画メーカー」を開発中。生成された企画をネット世代やα世代が評価し、フィードバックを反映することで、市場の感性をデータとしてチューニング可能にする仕組みです。畠山氏は「感性をデータ化することで、他社にはない独自のポジションを確立する」と語りました。
審査員の小池氏(THE CREATIVE FUND)から「感性AIの仕組み」や「人の手とAIの役割分担」について質問がありました。畠山氏は「データ収集や分析まではAIで自動化できるが、生成された企画の取捨選択は人の感性が担う。今後は蓄積が進むことで、さらに自動化の余地が広がる」と回答しました。
13 Smart Robotics Lab.(広島大学)(スマートロボティクスラボ)
先進理工系科学研究科 助教 島﨑航平氏
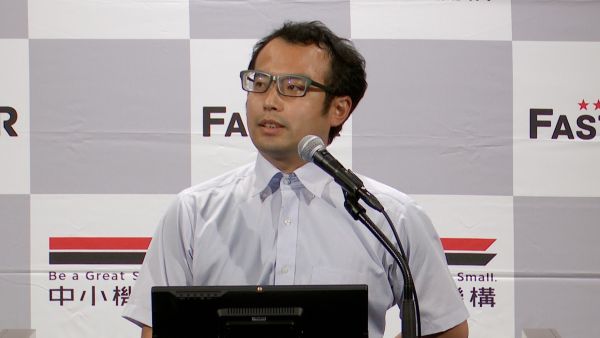
非接触振動監視で“見える”予知保全
広島大学 先進理工系学科 助教・島崎浩平氏が、プラント設備診断向けの「振動監視カメラソリューション」を発表。高速カメラ×画像解析で、センサーを貼れない高所・高温・高圧環境でも、広域を非接触で面計測し、設備の健康状態を“見える化”する。島﨑氏は、これまで振動計測と高速カメラを組み合わせた研究を行い、論文や特許、受賞実績を積み重ねてきました。今回のピッチでは「研究開発の社会実装を加速させるための創業」をテーマに発表。紹介された技術は、設備の劣化や異常を高精度に検出できるもので、従来型のセンサーと比較して広範囲・非接触でモニタリング可能という特長があります。これにより、プラントの稼働停止リスクやメンテナンスコストを大幅に削減できる可能性があると説明しました。島﨑氏は、今後の事業推進のために以下を募集していると述べました。
• 次世代型センシングデバイスの共同開発を担うフィールドエンジニア
• 設備の健康状態を管理するエンジニア
• グローバル市場展開を支える協業パートナーやリード投資家
また、これまでにNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)の事業や大学のGAPファンドなどの支援を受けており、国際展開・製品化を意識した研究開発を進めている点も強調しました。
審査員の浅田氏(One Capital) から「現在のプラント設備診断はどのように行われているか」の質問に、島崎氏は「従来はセンサーの常設や聴診棒による接触計測が中心だが、稼働中には適用できず、未把握の領域が多い。そこでカメラを用いた非接触型ソリューションの需要が高まっている」と回答。さらに「最初の導入先はポンプや配管など回転機械周辺を想定している」と説明しました。
14 株式会社FAI(ファイ)
代表取締役CEO 海老原寛氏

「性能から形を生む」生成設計で手戻りを根絶
「製造業を創造業へ」をビジョンに掲げる、名古屋大学発のスタートアップ。博士課程にルーツを持つ研究者を含む3名が中心となり、シミュレーション✕最適化を核に、製造業における大きな課題「手戻り(設計や生産工程のやり直し)」を根絶するソフトウェアを開発している。ピッチで海老原氏は、名古屋大学の認定スタートアップであることに加え、「トポロジー最適化を基盤に、複数の性能要求を並列的に満たす新しい設計プロセス」を実現する点を強調。従来の「一部性能だけを確認するもぐら叩き型開発」から脱却し、効率的かつ創造的な設計を可能にすることを説明した。
審査員の手塚氏(三井住友銀行)から「技術の本質や大手製造業との協業の進め方」について質問があり、海老原氏は「性能インプットから最適形状を自動生成する点が強みであり、現在は複数社とのPoCを通じて現場のフィードバックを反映しながら実装を進めている」と回答した。さらに海老原氏は、「我々はすぐ実用化できるテーマだけでなく、数学を基礎から深掘りし、時間をかけてでも本質的なイノベーションを起こすことを重視している」と述べ、研究と産業応用を橋渡しする独自の姿勢を示した。また、「将来的にはAIによる完全自動化を目指すが、それは人を置き換えるものではなく、人間の創造性を最大限に引き出す支援としてのAIである。資金はマーケティング強化と人材確保に充てたい」と展望を語った。
表彰式
全てのピッチ後、審査員および会場・オンラインの視聴者による審査を経て、以下の賞が贈られました。
One Capital 賞
受賞:Smart Robotics Lab.(広島大学)

【審査員 浅田慎二氏(One Capital CEO)コメント】
「たくさん質問させていただいた通り、すごく興味があります。大学発の研究を事業化に結びつける力、技術的なバックボーンがしっかりされていたことが決め手でした。おめでとうございます」
【受賞者 島﨑航平氏(Smart Robotics Lab.)コメント】
「このような形で受賞できるとは思っていませんでした。スタートアップは組織で戦い、様々な局面を打開していく忍耐力が必要になってくると思いますので、粘り強くこれからも頑張っていきたいと思います」
ロート製薬未来社会デザイン賞
受賞:ペンタリンク株式会社

【審査員 荒木健史氏(ロート製薬 CEO付兼未来社会デザイン室長)コメント】
「斜陽産業と言われてきた繊維産業を生糸で次世代成長産業にするという志とともに、その産業構造の原因を解明して、解決し始めているところに非連続の未来を感じました。また、生き物が好きな子どもたちが多く、キャリア観としても有望と感じました」
【受賞者 野中章生氏(ペンタリンク)コメント】
「このような形で評価いただき、大変光栄に思います。西陣織の伝統と最先端技術をつなぎ合わせることが私たちの使命です。受賞を励みに、さらにスピードを上げて事業化に取り組み、医療や環境といった社会的課題の解決に貢献していきたいと考えています」
THE CREATIVE FUND 賞
受賞:株式会社KeyWeave

【審査員 小池藍氏(THE CREATIVE FUND 代表パートナー)コメント】
「売上予測の数字はやや控えめに見えましたが、それ以上にチームの熱量と成長の可能性を強く感じました。地方から世界へ挑戦する姿勢は、まさに『グレートスモール』という言葉がふさわしいと思います。ローカルな価値をしっかり根ざしながらも、そこからグローバルに羽ばたいてほしい。次の世代を代表する存在になってくれると期待しています」
【受賞者 畠山雄樹氏(KeyWeave)コメント】
「地方から挑戦する私たちにとって、この評価は励みになります。SNSや広告代理の事業を通じて、人が本来持っている輝きを引き出し、それを社会に織り込んでいくビジネスを作りたいと考えています。今回の受賞を大きな一歩として、福岡・九州から世界へと挑戦を広げていきたいです」
三井住友銀行賞
受賞:株式会社FAI

【審査員 手塚崇之氏(三井住友銀行 成長事業開発部 副部長)コメント】
「まず、技術が非常にユニークで面白いと感じました。また、FAIのソリューションは、製造業の効率化につながるものだと思いますので、日本の産業競争力強化にもつながっていくような、広がりの可能性の大きさを感じ、選定させていただきました」
【受賞者 海老原寛氏(FAI)コメント】
「私たちの技術は、名古屋大学で培った研究をベースに、製造業の現場課題に真正面から取り組んできたものです。その現場に根ざした価値を評価いただけたことは非常に光栄です。今回の受賞を励みに、実装をさらに加速させ、製造業を“創造業”へと進化させる未来を実現していきます」
DCIパートナーズ賞
受賞:イルミメディカル株式会社

【審査員 成田宏紀氏(DCIパートナーズ 代表取締役)コメント】
「光学技術を基盤とした医療機器開発は、研究力の高さに加えて、臨床現場の課題を的確に捉えている点が素晴らしいと感じました。研究成果を実用化につなげるのは非常に難しい領域ですが、イルミメディカルにはその壁を越える力があると思います」
【受賞者 塚本俊彦氏(イルミメディカル)コメント】
「私自身、大手医療機器メーカーで新技術を開発する中で“事業化の壁”を痛感し、それを超えるために起業しました。今回の受賞は、医療現場の声を反映した製品開発が正しい方向に進んでいるという後押しだと受け止めています。これからも社会に必要とされる医療機器を生み出し、光で人の命を救う挑戦を続けていきます」
オーディエンス賞
受賞:株式会社esa

【オーディエンスコメント(会場・オンライン投票より)】
「循環型社会を担う技術としてわかりやすく、共感を呼んだ」「実際に手触りのあるリサイクル技術として、身近に役立つ未来が想像できた」など、多くの支持を集めました。
【受賞者 黒川周子氏(esa)コメント】
「会場とオンライン、両方の皆さまからこのように評価いただけたことは本当に嬉しく思います。廃プラスチックの問題は身近でありながら大きな社会課題です。私たちは“誰でも参加できるリサイクル”を合言葉に、再生素材を通じて循環型社会の実現を目指しています。オーディエンス賞という形で共感をいただけたことを励みに、これからも利用者やパートナーの皆さまと共に挑戦を続けていきます」
各受賞者には、それぞれ副賞として、1on1でのメンタリングの機会が贈られます。
最後に、独立行政法人中小企業基盤整備機構 創業・スタートアップ支援部 部長 石井芳明氏から、閉会の挨拶がありました。

「FASTAR第11期ということで、14社のピッチを皆さんに長時間聴いていただき、本当にありがとうございました。審査員の方々にも温かいコメントを頂戴し、感謝申し上げます。今回の登壇企業は、医療・ヘルスケア分野が5社、クリーンテック分野が4社、AI分野が5社と幅広く、先が長いテーマから直近で課題解決に直結するものまで多様でした。まさにイノベーションを通じて社会課題を解決していけるスタートアップだと思います。また、スタートアップは首都圏に7割集中していますが、今回は逆に7割が地方からの参加でした。地方発でグローバルに成長する企業が出てくることを、今後も引き続き応援していきたいと考えています」
閉会後には投資家・金融機関・事業会社など、スタートアップに関心のある方々と登壇企業による交流会が行われました。会場では活発な名刺交換や意見交換が続き、新たな連携や投資のきっかけとなる交流が数多く生まれました。オンライン参加者に向けても接点を提供し、幅広いマッチングを実現しました。