2025.01.17
イベントレポート
GRICトークセッションレポート【前編】「日本から世界へ~スタートアップによる次世代産業の形成~」
日本のスタートアップの今とこれから。さらに大きく貢献、そして世界へ羽ばたくために!
スタートアップによる産業形成を支援している「FASTAR(中小機構アクセラレーションプログラム)」。2024年11月12日、以下の<セッション参加者>の皆さんにお集まりいただき、トークセッションが開催されました。日本のスタートアップがもっと大きな貢献をするために、そして世界へ出ていくためには何が必要なのか、存分に語っていただきました! その様子をレポートします【前編】。
<セッション参加者>
インキュベイトファンド株式会社 代表パートナー 赤浦徹 氏

日本の将来を元気にしていきたい!独立系ベンチャーキャピタルです。「会社は探さない、0からつくる」がポリシーのインパクトビルドインダストリーズを掲げています。
将来宇宙輸送システム株式会社 代表取締役CEO 畑田康二郎 氏

元経産省官僚で、2022年に再使用型ロケット開発に取り組む企業を創業しました。FASTAR第9期プログラムに採択され、事業成長のサポートをいただきながら進めています。
経済産業省スタートアップ創出推進室 統括企画調整官 南知果 氏
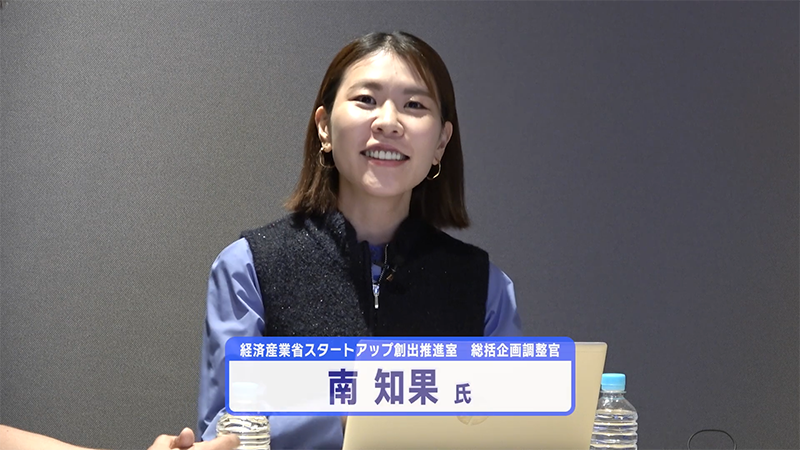
元は大手法律事務所所属の弁護士。新しいことにチャレンジしている人が好きでスタートアップ支援の道へ。米国留学を経て、国のスタートアップ政策を知り、2年前から現職です。
<ファシリテーター>
独立行政法人中小企業基盤整備機構 創業・ベンチャー支援部長 石井芳明 氏

15年以上、スタートアップエコシステムを盛り上げてきたという思いがあります。ゲストの皆さんとのセッションが非常に楽しみです!
スタートアップ、盛り上がっています! この10年で、投資額は約10倍にもなりました
【石井氏】
さて、今スタートアップ界隈、盛り上がっているというお話から。過去に比べて現状がどうなっているか、どう感じていますか?
【赤浦氏】
石井さんに出会ったのは17、8年前でしょうか。長くスタートアップ領域にいますが、昔と比べると確かに大きく変わってきていますよね。あの頃は独立系のベンチャーキャピタルってすごく少なくて、世の中的にはちょっと変わった人たちの集まりでした。でも今は、支援者側のベンチャーキャピタルも、独立系の個人が増えていて、100社くらいは増えた印象があります。
【南氏】
確かに、金額的にもこの10年でスタートアップの投資額は約10倍になったと言われています。2021年には、スタートアップは1万6000社ぐらいあると言われていましたが、今は2万社以上、約1.5倍に増えています。
10年ぐらい前は「起業家って変わっている人、変わった人がやる仕事」みたいなイメージだったのが、だんだん先輩の起業家が後輩に教えてあげることが普通になってきて、すごく数が増えているという印象はあります。
【石井氏】
経済産業省の資料でも、経済インパクトは大きいです。それから、人材が流動化しはじめているという話があって、本当にそういう意味で変わってきたな、と感じます。
考えてみると、まだ経済産業省にいた畑田さんと、2018年に一緒にやったのがスタートアップ支援プログラム「J-Startup」ですよね。
【畑田氏】
あの頃は、特に外国から見ると、そもそも日本にスタートアップなんてあるの?みたいな雰囲気でした。海外の展示会でバラバラに日本の会社がプレゼンしたところで、世界の中では埋没していました。ですので、そこにちゃんと旗を立てて、支援していこうっていうのがありましたね。
【石井氏】
そうですよね。8年かけて畑田さんがそれを一手に引き受けて、日本のスタートアップ政策を担う人だと思っていたら、ご本人が一気に踏み出して、実際に企業を走らせるという展開になっていました。それを後押しされた赤浦さんもすごいな、と思いました。
【赤浦氏】
畑田さんはもう超異例中の異例というか。エリート官僚が起業してチャレンジしているという、すごい事例ではないでしょうか。

スタートアップによる次世代産業の形成、その重要な柱は「宇宙」
【石井氏】
今日のテーマは、スタートアップによる次世代産業の形成ですけれども、そういう挑戦の中から産業が生まれてくるのではないかと思うのです。そして、その中の重要な柱が、「宇宙」だと思うのですがいかがでしょうか。
【畑田氏】
そう確信をしております。実は私、宇宙大好き少年だったり、ロケットを作りたいとかそういうわけではなくて。やはり経済産業省の国家公務員のノリで仕事をしているのですね。新しい産業をつくらなければいけない、これから日本が何で食べていくのか、ということがテーマなのです。
公務員の立場では、スタートアップの政策を20年かけて整備してきて、今では海外にも劣らないぐらいのいろいろな制度を作りました。ただ、そこに魂を込めるのはやはり起業家です。その数が増えていかないと新しい産業はできない。
その中でも、私は「宇宙」だと思っています。人の歴史は、移動の手段が多様化する中で発展してきました。飛行機や船ができたように、ロケットによる輸送も、確実に世界のインフラとして整っていきます。その時に、ちゃんと事業を作る人が出てくれば、世界の中で一定のプレゼンスは確保できるし、輸送手段が確立してくれば、ロケット研究者だけではなく、その町が発展していって、レストランができたりホテルができたり、いろいろな雇用が生まれていきます。波及効果もすごく大きいものだと思っています。
この「インフラを作る」という仕事は、国の仕事でもありますが、起業家が開拓していくことによって好循環が生まれるのではないかと考えたのです。

【石井氏】
小林一三(阪急電鉄創業者)の話を、ピッチでされていましたよね?
【畑田氏】
小林一三は、鉄道単体では絶対儲からないと言っていたそうなのですが、それによって郊外に住宅を販売することですごく儲かった。そして、そこに暮らす人が電車に乗ることで、鉄道事業もちゃんと儲かる。この相互作用を作ったところが、彼のイノベーションです。
ロケット開発も、国主導とか、大きな企業がものづくりだけをやっていても、確かに儲からないんです。そうではなくて、周りの人たちをいかに巻き込んで、いろいろなビジネスチャンスを作っていくか。これをスタートアップが旗を立てて、オープンイノベーションのきっかけを作っていく。そういうアクションを日本でも起こしていかないと、新しい産業は生まれていかないのではないかと思います。
【石井氏】
なるほど。赤浦さんも「次は宇宙ですよ」っておっしゃっていましたが、どういった思いで「宇宙」にかけようと思われたのでしょう?
【赤浦氏】
宇宙は自由にビジネスを発想していいところなのだな、と思ったのがきっかけでした。
僕が感化されたのは、株式会社アストロスケール創業者の岡田光信さん。2014年の2月だったと思いますが、スペースデブリ(宇宙ゴミ)の除去と、もう1つプレゼンをしていたんです。それは、ポカリスエットを月に持っていくから、大塚製薬さんからお金をいただいたという話で、それにすごく感化されました。何をやってもいいんだな、と。
その後、株式会社ispaceに出会い、そこから宇宙船を作ろうっていう提案をするんです。1回50億円、1回で失敗したら困るので2回分の100億円。その調達を2年がかりでやるのですが、それを成功させるには、法律の整備も必要だということがわかりました。
そこで内閣府にお願いに行ったのですが、そこの宇宙開発戦略推進事務局っていうところに、すごいイケてるかっこいい人がいまして、日本を元気にするビジョンを持っていて、それがあの畑田ビジョンだったんですね。
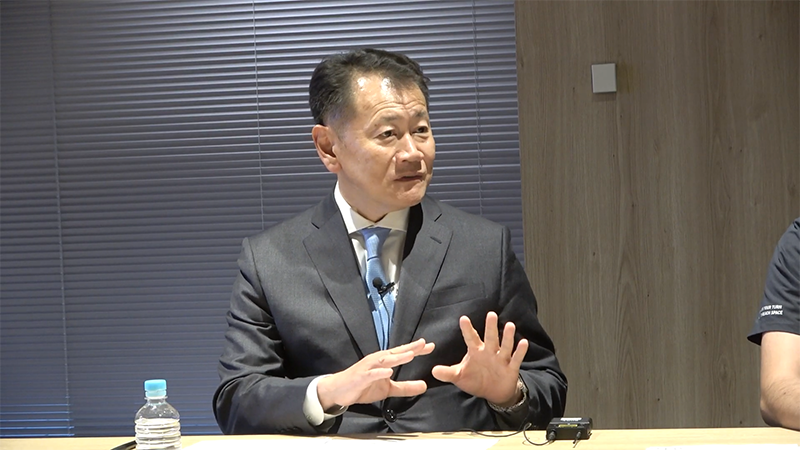
【石井氏】
なるほど。
【赤浦氏】
それで、その時に初めて畑田さんにお会いしたのですが、うまく付帯決議に通していただきました。その頃、ニュースペースの宇宙スタートアップはあまりなかったのですが、1社ずつ増やしていって、結果として横がすごく繋がっていきました。お互いがお互いを必要とし合いながら、一緒に盛り上げていっている。これが産業化なのかなっていうのがあります。
【畑田氏】
2015年ぐらいの頃、私も宇宙ベンチャーに会いに行ったら、1ヶ月ぐらいでほとんどみんなに会えてしまうくらい、すごく小さなコミュニティでした。もっと増やそうということでビジネスアイディアコンテストを行いました。
今は100社を超えるくらい出てきて注目されつつありますし、その中でも赤浦さんは早い段階で大きく投資して加速させたものすごく強力な支援者でした。
各省庁からの注目度もアップ!スタートアップが個別産業の軸になりつつある
【石井氏】
経済産業省でも、航空機武器産業課の方から、「大手重工ももちろんだけど、最近はスタートアップの方とよく話すんです」という話が聞こえてきて、政策的にもスタートアップが個別産業の軸になりつつあるように思うのですが、南さん、どうですか?
【南氏】
まさに今、各産業政策の中にスタートアップの要素をビルトインしていくといったことが、経済産業省でなされていると思います。
例えば、今力を入れている政策としてGX(グリーントランスフォーメーション:脱炭素)がありますが、大企業が脱炭素していこうということだけではなく、スタートアップが新しい技術やアイデアによって、どう脱炭素を進めていけるか、その支援も考えています。
創薬の分野でも、研究開発を支援するというだけではなく、スタートアップ企業を産業政策の中に埋め込んでいく感じになっているように思います。
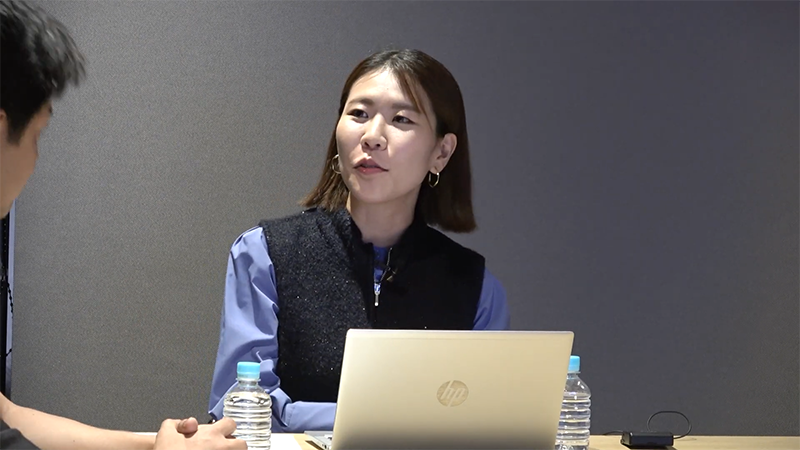
【石井氏】
確かにそうですね。創薬の分野も、グローバルな新薬の開発を待つよりは、スタートアップでやるようになっています。販売は大企業でも、創薬の8割はスタートアップ由来になっている、みたいな話もありますね。
各産業において、新しい分野に出資したり人材を投入したりすることが、大企業ではなかなか難しい時代になってきています。だから「宇宙」といった分野で、スタートアップの役割が強くなってきたのだと思います。
【赤浦氏】
きっかけは多分、「ベンチャー・チャレンジ2020」ですよね。省庁横断で各省庁の方々が内閣府に集まりました。僕がそのとき言ったのは、重点領域を決めるべきだということ。当時の世耕経済産業大臣が、そこに「えこひいき」という言葉を用いて、そこから生まれてきたのが「J-Startup」ですね。その中で1つの重点領域として宇宙を選んでいただいた結果が、今に繋がっているのかな。
【石井氏】
覚えていてくださってありがとうございます。「ベンチャー・チャレンジ2020」の時は、各省庁の方々にテーブルに着いてもらうことがまず大きな目標でした。そのときから比べると、今は本当に風向きが変わって、追い風が強いです。今は、各省庁から「スタートアップを一緒に支援したい」とか「どうやってコンタクトすればいいか」という問い合わせがとても多くなっています。
【南氏】
最近の驚きとしては、防衛省がスタートアップに関する会議体を開いているということ。日本の防衛産業の中で、どうスタートアップに活躍していただくかを議論しているそうです。これは、すごく新しい流れだと聞いています。
【石井氏】
そうなんです。防衛省も、以前は無理矢理乗り込んでいって意見交換するぐらいだったのですが、今はお互いの課長級、それ以上の方が集まる会議を定例的に行っていて、本気でイノベーションをやろうとしている空気が伝わってきます。
【南氏】
WOTA株式会社の水再生システムの、水を循環して汚い水をキレイにするという技術が、例えば被災地で使えるとか、実際スタートアップの技術が現場で活用できるということも広がっています。
【石井氏】
WOTAは、僕も東大の研究室に見にいきました。当時は実験機器みたいな感じでしたが、今は能登半島地震の被災地域でも大活躍だし、もう一般的に広がってきましたよね。ああいうのを見ると、スタートアップがいろいろな貢献をするということが、よくわかってくる。
後編へ続きます。
> GRICトークセッションレポート【後編】はこちら