2025.01.17
イベントレポート
GRICトークセッションレポート【後編】「日本から世界へ~スタートアップによる次世代産業の形成~」
スタートアップによる産業形成を支援している「FASTAR(中小機構アクセラレーションプログラム)」。2024年11月12日に開催された、トークセッションの様子をレポートします【後編】。
> GRICトークセッションレポート【前編】はこちら
「嫁ブロック」はもう古い?! 大企業からスタートアップへの人材流動が起きている
【石井氏】
各省庁が注目するスタートアップも出てきて、産業を作る動きが加速する中で、やっぱり人材が大事だと思います。成長を支えていく人の動きが、今後どれだけ広がるかというところですが、畑田さん、どうですか?
【畑田氏】
そうですね。当社も2022年の創業以来2年半くらいで、直接雇用した従業員が70人ほどおります。4割ぐらいは宇宙業界や航空業界出身の方ですが、それに対し残りの6割は、自動車メーカーなど宇宙業界以外の人材が飛び込んできてくれています。
面接で、「奥さんとか反対しませんか?」と聞くと、むしろ「今の企業で腐ってる場合じゃない。あなたは宇宙開発やりなさい」みたいな、「嫁プッシュ」が起きているというんです。もうブロックはされない感じになっていて、スタートアップを見る目が変わってきている。これまで大企業でメインプレーヤーだったような人が、ポジティブにチャレンジするところになってきたのかな、と感じます。
【石井氏】
嫁ブロック、旦那ブロック、親ブロックの世界だったところが、見方が変わってきたのですね。
とはいえ、大企業から来た人がスタートアップで働くのって、どうでしょうか? 企業で役割を果たしてきた人が、新しいカルチャーを作るところに、必ずしも慣れているわけではないですよね?
【畑田氏】
そこは現在進行形で挑戦しているところではあります。ただ、元々経済産業省で働いていて、そこから起業した私の感覚としては、経済産業省での経験ってすごく役に立っています。経済産業省って、2年とか短いサイクルで異動するので、ネガティブに言われがちなのですが、毎回新しいことをフレッシュに考えることができるのはいい経験でした。意外と役所の人ってオープンマインドだし、本質的に新しい仕事に向かっていくことができる。今も、人事異動して宇宙産業化をやっているような感覚です。
【石井氏】
南さんはどうですか?
【南氏】
私自身のキャリアで言うと、大手の法律事務所で弁護士を辞めるときが一番ハードルが高くて、経済産業省に入るときの方がハードルはありませんでした。1回どこかに飛び込んでしまうと、意外と次のチャレンジってできるんだなと思いました。大企業にいると、自分の人生プランを捨ててスタートアップの世界に入るのはすごく勇気がいることだとは思いますが、意外と何とでもなります。
【畑田氏】
大きな組織にいると、キャリアの自主性がなくなるというか、上から言われてやる仕事に慣れすぎて、自分でやりたいことがなくなっていく。それは結構リスクだと思うんです。辞めると、自分で自分の仕事をどうするか決めていくしかない。やってみると、自分がやりたいこととやる仕事が一致していくので、むしろ快適です。でも、最初は怖いですよね。仕事が与えられないって、どうしよう、みたいな。自分の仕事は自分で作る。自分でやった方が楽しいと思います。飛び込んじゃえばね。
【南氏】
それと、私はそもそも起業家やスタートアップで働く人たちが好きです。新しいことを企んだり、社会を変えようと本気でやってる人が多くて、そこに魅力を感じる。ちょっと青臭いところに魅力を感じる人は、どんどんスタートアップに入ってきたらいいと思います。
チャレンジしている人が報われる社会へ。インセンティブ制度も世界レベルに充実
【石井氏】
僕が印象深かったことは、インパクトスタートアップ業界のメンバーの中で、世界的な投資銀行を辞めてスタートアップにいったCFOの方がいたのですが、その人が「お給料は3分の1ぐらいだけど、世の中に対して誇れる、自分の家族に誇れる仕事ができている」という話をしてくれました。そういう話を聞くと、僕は行政官として一緒に頑張りたいと思うのですが、とはいえ、お給料の話も大事だとも思います。
南さん、給料の話といえば、ストックオプションですよね?
【南氏】
成功したときに、ちゃんとプラスアルファがあるっていうのは大事だと思っています。最近のスタートアップは決してお給料も安くなかったりしますが、ベースのサラリーは下がってしまう人もいると思います。でも、社会全体として、頑張って努力して、リスクを取ってチャレンジした人には、プラスがあるようにしたいですね。
スタートアップが活用しやすい手段として、ストックオプションは大事だと思っていて令和5年度、6年度と改正をして、税制も変わりましたし、産業競争力強化法でも、取締役会でストックオプション発行をしやすい制度を創設しています。
どういう人にどういうふうにインセンティブを持って仕事をしてもらうかは、経営者としての腕の見せどころだとも思います。制度改正によって悩む部分も増えているかと思いますが、組織をどう作っていくか、社員のメンバーにどういうふうに仕事をしてもらうのか、経営者の方々に考えていただけるきっかけにもなるのかな、と思っています。
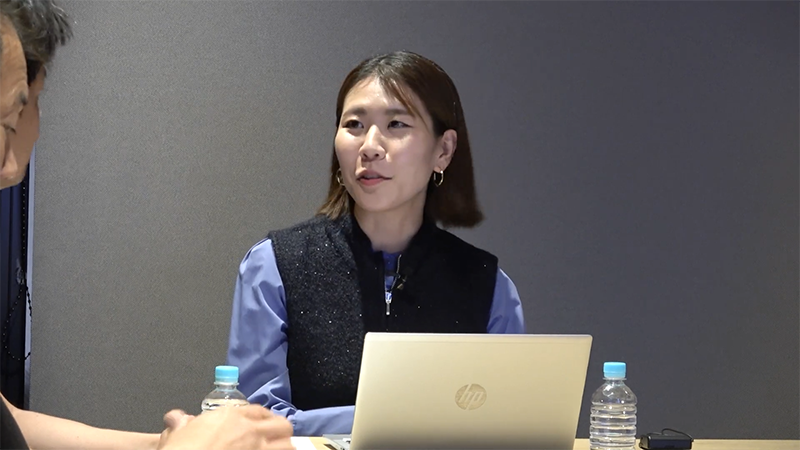
【石井氏】
インセンティブ面では、世界でもトップクラスの制度になってきた感じですよね。
【畑田氏】
リスクを取って成功したら、ちゃんと大きな報酬が得られるようになった方が、絶対に健全。報酬的な意味ももちろんありますが、日本全体で企業の価値そのものを上げていかなければいけないし、その動機づけは、絶対あるべきだと思っていました。
大企業でも、単に売り上げを上げていけばいいのではなく、その会社が投資家からどう見られているか、何が期待されている会社で、会社の価値そのものを上げた方が得られるものも多い、というふうに変わっていけばいいなと思います。
スタートアップはいらない?! 大企業のスタートアップ化こそが、日本経済再生のカギ
【石井氏】
そういう動きをもう少し大きな視点で見ると、大企業がスタートアップになっていく、あるいは大企業がスタートアップをM&Aして、大企業の中にスタートアップの島をどんどん増やしていく、そういうことも大事なのでしょうか?
【畑田氏】
スイングバイ(スタートアップが一時的に大企業の傘下に入る)などもありますが、赤浦さん、その辺りいかがですか?
【赤浦氏】
極端な話をすると、もうスタートアップはいらないと思っています。日本経済の再生のためには、大企業をどうにかすることを真剣に考えた方が、インパクトは大きいとは思います。
今の大企業って、法人税率も下がって、内部留保もどんどん増えていっていて、人材だって優秀な学生は大企業に向かわれる方が多い。ただ、もう戦後長く経ち、大企業だと、ある程度人事の決まった型の中で、大きな勝負をせずに守りに入っていた方が無難だったりします。でも、その無難をやって、日本は失われた30年になっちゃったわけです。やっぱり大胆な経営をしていけるようにした方がいいのではないか、と思います。
シンプルに言えば、ノンコア事業を売ってコア事業を買うという選択と集中を、大企業こそやっていくべきということ。日本の産業の構造を変革していくべきじゃないか。そのときに、売るノンコア事業があるなら、スタートアップで買いますよ、と。そういう刺激をすることで、大企業を変革した方が、絶対インパクト大きいですよね。
畑田さんが2年で70人採用したって話がありました。大企業から、しかも理系のエンジニアサイドの人たちを多く採用しています。スタートアップと大企業間でも人材が動くようになってきている。これって、すごいインパクトです。そこを還流するなり流動化するなりが、今の日本の課題だと思う。大企業は今の仕組みを一度解体して再構築していく。いろいろなところに優秀な方々や思いのある方々がいらっしゃると思うので、世の中を変えてやろうという力が合わさるといいな、と思います。
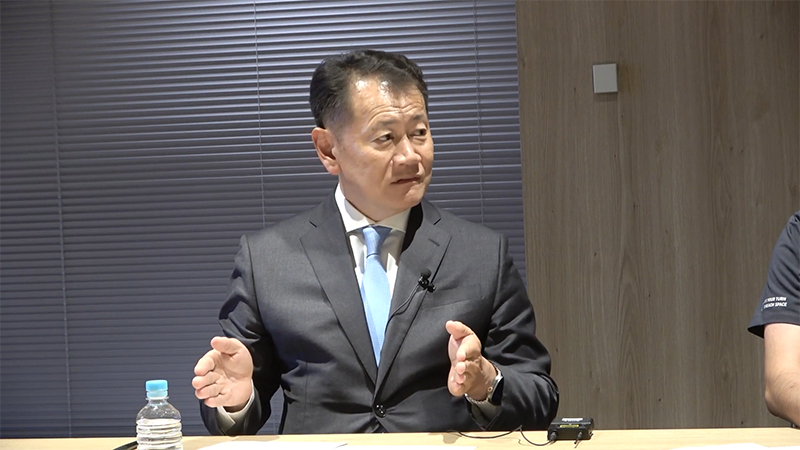
【石井氏】
スタートアップが盛り上がってきて、軸ができるようになってきたのでしょうね。そうすると、大企業がスタートアップ化する、スタートアップとくっついていく、あるいはスタートアップを中に入れていく、そういう変革の軸に変わってくるのではないかと思います。
中小企業基盤整備機構でも応援するし、経済産業省でも推して、企業は企業で変えていく。それを前向きに捉えてやっていきたいですね。
日本の技術・ものづくりで世界をリード! 次世代のヒーローとなる産業形成を
【石井氏】
もうひとつ確認しなきゃいけないのが、世界での立ち位置です。グローバルに日本が貢献する、日本が競争に勝っていくという観点で、何が必要だと考えますか?
【赤浦氏】
昔、日本は強かった。それが弱くなっちゃった。失われた30年です。
強かった時代には、自動車エレクトロニクスを中心に、世界の時価総額トップ10のうちの半分が日本の銀行だった。要は、ITの時代に負けてしまったんです。この30年のタイムパラダイムでみたら、勝った30年があって、負けた30年があって、次の30年のパラダイムを産業形成で捉えにいけばいいんです。
次のパラダイムは、情報産業の次の「脱炭素」という文脈なのだと思います。その領域にいったとき、例えば半導体でも、水素でも、電池でも、ありとあらゆる分野で日本の技術やものづくりに再び脚光が当たって、世界をリードしていける可能性がある。そういう新しい潮流をリードしていく産業と企業を日本からつくって、世界に羽ばたくことが必要なのではないか。
それを支援するのも、昔は日本銀行だけでしたが、今はベンチャーキャピタルも頑張っています。そこは日本の銀行とベンチャーキャピタルと、また国とも連携しながら、新しい世界のヒーロー、次世代のGAFAを日本から作ることが必要なのかなと思います。
【石井氏】
畑田さん、どうですか?
【畑田氏】
当社も、アメリカのスタートアップとかイギリスのスタートアップとかと連携をして、一緒にやっています。あるところは戦っていく部分も当然あると思いますが、なにも全部オールジャパンでやらなきゃいけないということではなく、組めるところは組んで、自分たちの強みを特化していくという形も、これから必要になってくると思っています。
日本って海外のものをキャッチアップしながら、どんどん洗練していって世界で勝つ、そういうパターンだとも思います。謙虚に海外から学ぶというところも、同時にやっていければと思います。

【石井氏】
なるほど。南さん、どうですか?
【南氏】
まさに畑田さんの会社みたいに、最初からグローバルを目指してるようなスタートアップがどんどん増えればいいなと思います。経済産業省にいても、海外の投資家の方々からのお問い合わせがすごく増えていているんです。日本の株式市場は世界から注目されていて、投資対象として日本を見ている海外の方が、アメリカのみならず、ヨーロッパやアジアでも増えていると感じます。それをきっかけとして、日本からグローバルに出ていく企業がどんどん出てくればいいなと強く思っています。
1人1人の力で、世の中を変えていく。チャレンジして行動していく人を増やしたい
【石井氏】
最後に、一言ずつメッセージをいただけますか?
【赤浦氏】
どうせ1回の人生です。しかも、宇宙の歴史から見たら、バリバリ働ける期間なんて、あと5年か10年、あと50年あったとしても、誤差ですから。どうせなら、世の中を自分が変えてやるんだという思いで、チャレンジしても楽しいんじゃないかなと思います。
今、停滞感があるところから、再び次の30年に向かおうという時代の変革期です。時代の変革期にはパラノイアが出現すると聞いたことありますが、つまり、狂ったもん勝ち。ぜひ、チャレンジしていただきたいなと思います。
【畑田氏】
大企業かスタートアップか、ということではないと、私は思います。最強なのは、大きい組織に属していながらスタートアップ的に動ける人。大きな企業のリソースをフル活用して、いろいろなことを好き放題できる人が、一番強いです。
私は経済産業省にいたとき、いろいろリソースを使ってスタートアップを支援することがすごく楽しかった。必ずしもみんながスタートアップをやらなきゃいけないということではないし、大企業の組織の論理をわかっている人がスタートアップ側にいるというのも、また大事です。
ですので、あまり二者択一で考えずに、今いるところで一番価値を発揮できるのはどういう行動かを考えることが大事なのかな、と思います。
【南氏】
結局のところ、大事なのは、1人1人がどういう行動を選択してやるか、ということ。スタートアップの会社を見ていても、1人入るだけですごく会社の雰囲気が変わったり、その人の活躍でいろいろなことが変わったりするので、人1人の行動力というのは侮れないと思います。いろいろなところで活躍している人たちが混ざっていくことも大事ですし、私自身も、そういう人を混ぜるようなところで貢献していきたいと思っております。
【石井氏】
ということで、素晴らしいお話をいただきました。私からさらに付け加えるとするならば、この話が良かったと思った方は、行動に移していただきたいということです。一歩前に出るということを、ぜひみんなでやっていければと思っております。
「評論家であってはならない、公の支援者としての矜持を持って支援するべきだ。」
私たちは、そういうチームを作って、スタートアップの支援をさらに強化していきます。
本日は、ありがとうございました!
今、まさに行動して変革しようとしているゲストたちの白熱したトークセッション、いかがでしたでしょうか?
中小企業基盤整備機構ではスタートアップを伴走支援するアクセラレーションプログラムである「FASTAR(ファスター)」事業を実施しています。頑張る人を伴走して支援するプログラムです。ぜひ、ご活用をお考えください。