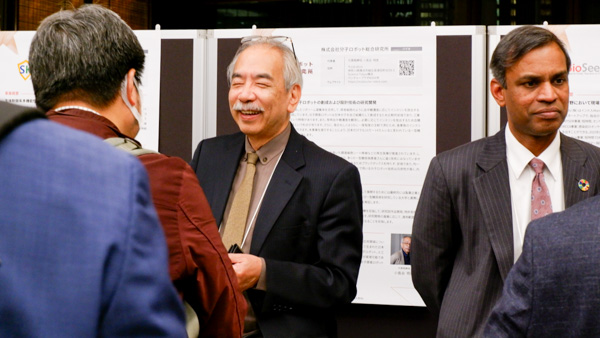2025.03.25
イベントレポート
アクセラレーションプログラム FASTAR 10th DemoDay(後編)
「FASTAR」とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施するアクセラレーションプログラムです。
> FASTAR 10th DEMODAY イベントレポート【前編】はこちら11.株式会社KAMAMESHI

11社目は、株式会社KAMAMESHI(Website ) 代表取締役CEO 小林俊氏です。
小林氏は、「日本の製造業現場では設備の老朽化が進み、部品調達ができずに復旧できないケースが発生しており、逆に使われない予備品が滞留・廃棄されている」という現状から、製造業のための部品プラットフォーム「Kamameshi」を立ち上げました。
「Kamameshi」は、必要な部品と提供可能な企業をマッチングさせる、製造業版「メルカリ」のようなサービスです。ビジネスモデルは、会員企業からの年間システム利用料で、設備保全の技能人材を有しており、現場の調査、教育指導、部品在庫管理のためのシステム提供も併せてサービス展開しています。
すでに売買サイトに2,000部品、社内在庫登録品は10万点を超える在庫管理システムとなっています。社内在庫をウェブ上で管理でき、製造終了のリスク管理も可能です。
2024年4月のサービス開始から100事業所以上の会員を獲得し、2024年度は5,000万円の売上を見込み、2028年度には2,500事業所、70億円の売り上げを計画しています。高い目標達成のため、日系海外進出先での展開など、スケール化を図ります。また、設備保全サポートシステムと、製造業ECモールの新サービスの提供開始も予定しています。
春原氏から「中古品を扱うということで、悪質なものなどはどうやって防ぎますか?」との質問があり、「会員登録制にしているのは、安全性を担保するという意図があります。最初に取り交わす利用契約には、部品の補償なども織り込んでいます。また、システム上のマッチングだけで売買成立にせず、実際の現場で判断できる仕掛けを作っています」との回答がありました。
12.Stay to Stay株式会社

12社目は、Stay to Stay株式会社 CEO 山川雄一郎氏です。
同社は、空き家問題において、「市場に出回っていないこと」「観光資源としての伝統的建築物の取り壊し」を社会課題として認識し、家主への空き家活用商品の提供、古民家デザインの高級ホテル・民泊の提供を行っています。空き家を高級民泊に再生し、会員権を販売し、売上をリフォーム代として空き家オーナーに提供するモデルです。
家主のメリットとしては、リフォームの負担がなく固定資産税の支払いが不要、家主も最大185日利用可能、定期借家で12〜15年で家主に返還となることが挙げられます。
会員へのメリットとしては、多人数の宿泊利用が割安であること、年1回以上の宿泊権利の確保が可能となることがあります。また、国交省からノーアクションレターにより承認を受け、全国で初の民泊家主同士の民泊規制期間中でも民泊稼働期間にカウントされない定期貸し合い交換仲介も可能となり、日本の民泊事業進出者を大きく増やすと見込まれており、いずれもビジネス特許出願中です。
山川氏によると、「特に多人数で宿泊する場合に質に比した価格メリットがあり、主にアジア圏の富裕層や大人数で泊まる文化のある国に高いニーズが見込まれる」といいます。売上としては、5期目で2,000棟、4,800億円を計画しています。また、前職で共同設立した米国の会社で開発された世界最高性能のデプスセンサーの応用製品開発ライセンスを受け、開発中のWeb3
IoT AI Agentセンサーシステムネットワーク技術を活用した地域の安全・QOL向上、経済価値の向上を目指すデジタルツイン事業も推進中です。
朝倉氏から「想定される一等地の高級な空き家はどのくらいあるのか?
また1泊あたりの料金はどのくらいですか?」との質問があり、「物件は空き家全体の1%以下です。1泊料金は17〜20万円ほど」との回答がありました。「IoTセンサーネットワークのところはどう繋がっているのですか?」という質問には、「住宅の交換を仲介するとなると保険が重要。プライバシーを侵害せずにセンサーをつけてもらい、保険の支払いがスムーズになるサービスです」という回答がありました。
13.株式会社OCT-PATH

13社目は、株式会社OCT-PATH(Website ) 代表取締役CEO 多田雄策氏です。
同社はブロックチェーン開発をメインに、AIの開発も行っています。既存事業としては、NFTのマーケットプレイスを中心に展開しています。独自のウォレット機能など、企業向けにカスタマイズ可能なパッケージを提供しています。現在、日本特化型のマーケットプレイスの構築や、大手小売事業者との共同プロジェクトなどが進行中です。
新たに自社サービスとして、ブロックチェーンゲーム領域への参入を予定しています。ブロックチェーンゲームとは、ゲームをプレイして収益を得られるようなもののことを指します。日本市場は930億円で、多田氏は「このうちの30%を狙っていく」と話します。
参入チャレンジするための技術ハードルが高いため、同社ではゲーム開発者がブロックチェーン技術を容易に導入できるよう、マーケットプレイスのAPIとSDKを提供するなど、支援ツールの提供をしたいと考えています。
ビジネスモデルは、SDKの利用料やマーケットプレイスの売買手数料となります。また、UnityやUnreal
Engineに対応した開発環境を整え、ユーザビリティの高い機能を提供します。今後7年で、20億円の売上を目指しています。
朝倉氏から「ブロックチェーンゲームの何が良いのか?」との質問があり、「プレイして稼ぐのがメインで、事業者がトークンの価値をあげる、プレイヤーが盛り上げる、といったみんなでサービスを作るところが良いところ。ただ、楽しめるゲーム自体は少なく、優れたゲームの開発が必要なので、その支援をしたいと考えています」との回答がありました。
14.株式会社レクリエ

14社目は、株式会社レクリエ(Website ) 代表取締役兼CEO 檜垣嘉孝氏です。
同社は広島県発のシステム開発会社で、画像認識AIを使ったインターネット上の類似画像発見システム「ガードアップPRO」を開発しました。
画像の無断転用は、東京オリンピックのロゴ問題などあらゆる組織で発生しており、画像盗用の権利侵害・賠償は、近年大きな課題となっています。
「ガードアップPRO」は、画像を無断転載しているか・されていないかを自動で検出し、状況を可視化することで、画像コンプライアンスリスクを大幅に削減します。画像転載元URLや損害賠償基準額の確認、対応状況のセグメント分けなどができ、ユーザビリティの高いUI設計になっています。プランには、SaaS、委託、スポットがあります。
テストマーケティングの3ヶ月間で、12の自治体でトライアル導入、民間企業3社でも有償導入が始まっています。檜垣氏は、「今後、WordPressのプラグイン化、サイト内画像の自動抽出技術、さらに動画の検出にもフィールドを広げていき、全コンテンツの検出が
1ツールで行える未来を作り、あらゆる無断転載の防止を目指します」と述べ、「2030年のIPOを契機に、無断転載リスク対策の必須AIツールに成長させたい」としました。
朝倉氏から「実際、無断転載の損害賠償額の合計はどのくらいですか?」との質問があり、「民間における損害賠償額の測定は困難ですが、報道にもあるように、自治体では損害賠償が多数発生しています」との回答がありました。「現状の汎用型AIでも検出できるのでは?」という質問には、「使用しているのは汎用型AIですが、業務効率化SaaSとしてユーザビリティの部分で差別化を図ったり、動画の類似検出にもフィールドを広げたり、WordPressプラグインによる普及を考えたりしています」と回答しました。
15.株式会社TIMEWELL

15社目は、株式会社TIMEWELL(Website ) 代表取締役CEO 濱本隆太氏です。
同社は「世界No.1の挑戦インフラを作る」をビジョンに掲げ、共同創業者2人の経験を活かし、イベント運営を効率化するソリューション「TIMEWELL BASE」を提供しています。
主なターゲットは、年間1回以上のイベントを定期的に企画運営している組織で、プログラムの企画、運営までを一元化・自動化することで、煩雑な業務工数を最小化します。また、コンテンツの再利用とデータ活用により、プログラム開催の成果を最大化します。
競合他社がチケッティングに集中している中、同社では実際の業務を効率化する機能を充実させています。参加者、登壇者への依頼、謝礼支払い、イベントレポート記事作成までの対応を行うことができ、決済部分での課題解決のほか、プロジェクトマネジメントの課題まで、一貫したソリューションを提案できるのが強みです。
ビジネスモデルとしては、イベント運営者やイベント支援事業者へのサブスクリプションでのサービス提供となっています。濱本氏は、「今後はマルチエージェントとして、さらに高度な支援と効率化を実現していきます」と締めくくりました。
津田氏から「実際の利用者からの声はありますか?」との質問があり、「運営者が困るのは、実務より関係者とのコミュニケーションコストで、なかなかレスがこないといったことや、ヒューマンエラーが生じること。それらを削減でき、参加者とのコミュニケーションなど本質的な仕事に集中できるところが好評です」との返答がありました。
16.codeless technology株式会社

16社目は、codeless technology株式会社(Website ) 代表取締役 猿谷吉行氏です。
同社の製品「そのままDX」は、現場で山積する書類をデジタル化し、世界一簡単なDXを実現するために開発されたツールです。創業者の猿谷氏は、10年間のスマホ修理店舗の運営経験から、書類をシステム化する難しさを痛感し、このサービスを考案しました。
このツールでは、紙の書類を写真に撮って送るだけで、AIと人が分析し、最短1時間で入力フォームを自動生成します。元の書類と同じ見た目で使用でき、タッチペンや音声、キーボードなどで手軽に入力が可能です。また、データベース管理が可能で、APIやCSVで出力できます。つまり、現場側では使い慣れた書類と同様のフォームとなり、管理者側では手軽に利用できるデータベースとなる、全く新しい管理ツールが出来上がります。このサービスは、すでに特許出願も完了しています。
翌日から運用を開始できる迅速な導入が特徴で、製造業や市役所にて導入実績があります。2023年末のリリース後、300社以上に導入され、高評価を受けています。さらに、多言語対応が可能で、海外展開も進めています。猿谷氏は、「今後は、協業や人材募集を進め、世界一簡単なDXの実現を目指します」と、力を込めて話しました。
加藤氏から「データを解析に使いたい時、分析のしやすさに工夫はありますか?」との質問があり、「自由な形式で並び替えができ、CSVに出力することもでき、APIにつなげていくこともやっています。データベースの見方がわからない企業にはサポートも行っています」との回答がありました。また、「需要が見込めるのはどういった会社ですか?」という質問には、「病院など自分たちが想定していなかったところで使いたいという声があるが、営業戦略として、今は製造業で実績を作っていこうとしています」という回答がありました。
17.株式会社KNiT

17社目は、株式会社KNiT(Website ) 代表取締役 窪内将隆氏です。
同社のAI画像解析プラットフォーム「GeXeL(ジクセル)」は、研究開発向けに作業効率を大幅に向上させるサービスです。創業者の窪内氏自身の経験から着想を得たもので、「従来は物差しを使ってディスプレイ上の粒子の数や長さを手作業で測定していましたが、この作業を90%以上削減でき、研究開発全体を加速化させることができる」と言います。
ステップ1は、画像をアップロードするだけで、AIが自動的に解析し、数値データを迅速に返却するサービスです。これまでのAIでは誤認識がありましたが、大幅な精度向上を実現しています。大手の研究開発部門で導入が進んでおり、月額5〜30万円のプランを提供しています。ステップ2は、AIが実験条件を提案するという機械学習サービスです。研究者は試行錯誤の実験回数を減らし、効率的に開発を進めることができます。ステップ3は、収集データの効果検証を提供する高付加価値サービスの提供です。今まで解析できなかった画像を数値化して因果関係を明らかにし、新しいサービスを作っていくといった展開を考えています。
シリーズAの資金調達を開始し、1年後に1億円、2年後に3億円の売上を目標としています。
朝倉氏から「今後、技術革新によってジャンプされることはないですか?」という質問があり、「研究分野では、顧客ごとの画像に適切なAIが必要になりますが、ネット上には教師データがなく、作成は容易ではありません。我々は半自動で教師データを作成しているので、多種多様な精度の良いAIを用意できることが強みです。コモディティ化の懸念はありますが、研究業界は先行優位性が大きいです」との回答がありました。
18.株式会社Onikle

18社目は、株式会社Onikle(Website ) 代表取締役 立野温氏です。
「企業内での情報検索に、業務時間の約20%の時間が費やされている」と、立野氏は現状の課題を示し、「この背景には、社内アプリの増加やチャットツールの利用により、情報の所在が分かりにくくなっていることがある」と言います。
この問題を解決するために、同社では、社内情報版Googleのような検索ツールを提供しています。このツールはMicrosoft
365やSalesforceなど複数のアプリとAPI連携し、情報を一括で検索可能にします。既存のサービスとは違い、フォルダ整理が不要で、すぐに使い始めることができます。OCR機能により、画像内のテキストも検索対象となります。さらに、権限管理にも対応し、ユーザーによって検索結果が異なり、機密情報にも対応しています。
利用プランは、1IDあたり月額5,000円の固定プランと、データ量に応じた従量課金プランを用意しています。現在は上場企業にて採用されており、今後クラウドデータ量の増加に伴って市場規模の拡大が見込まれています。
立野氏は、「筑波大学発べンチャーとしてチームで、『繰り返し作業を機械化する』をビジョンに進んでいきます」と意気込みを語りました。
沼田氏から「開発が難しかった点は?」との質問があり、「API連携は1つ1つのアプリごとに形式が異なるので、地道に作っていった。それが競合優位性につながっていると思います」との回答がありました。「ターゲットは基本的にエンタープライズでしょうか?」との質問には、「エンタープライズが魅力的な主力顧客です」との回答がありました。
19.株式会社Geek Guild

19社目は、株式会社Geek Guild(Website ) 代表取締役CEO 尾藤美紀氏です。
尾藤氏は、元アドビシステムのプロダクトマネージャーとしてインターネットの革新を目の当たりにした経験から、AGI(汎用人工知能)に注力しており、日本のデータが海外に流出する現状を危惧し、日本企業としてAGIを構築するという強い信念を持っています。
同社の「キャッシュAI」は、100%の正当率を誇るAIです。ハッシュ値を用いたテーブル構造にしたことにより、誤回答を防ぎ、医療や金融など正確さが求められる分野での活用が期待されています。生成AIと組み合わせることでセーフティーフィルターとして機能します。
元々は、小型化を目的としてAIモデルの中間層の100階層をテーブル構造にしたもので、複数ステップの計算を効率化し、サーバー使用時間とコストを90%削減します。この技術はすでに20社以上で採用されており、「間違えないAIオペレーター」として提供しています。それにより人件費を60%削減することができると言います。
米国をはじめ、複数の国で特許を取得し、海外展開を加速しています。市場規模は生成AI全体の0.2%としても130億円あり、さらなる成長と市場拡大を目指しています。
春原氏から「銀行にもニーズがあると思いますが、どういう活用が可能ですか?」との質問があり、「現在はAIオペレーターの提供に絞っていますが、銀行でも電話対応が可能です。また、サイバー攻撃も防げます」との回答がありました。沼田氏からの「なぜ正答率100%で小さいモデルを構築できたのですか?」との質問には、「ハッシュテーブルにして処理速度をあげています。テーブル内にないものは、回答なしとなる仕様です」との回答でした。
表彰式
全てのピッチを終え、審査員及び会場、オンラインでの視聴者による審査が行われ、受賞者の発表となりました。
アニマルスピリッツ賞
受賞:アイティップス株式会社

【朝倉氏コメント】
「アニマルスピリッツは、未来世代のための社会変革という理念を掲げており、日本が抱える課題に取り組む皆さんを重点的に応援したいと思っています。日本の超高齢化社会の中、アイティップス株式会社が取り組んでいる領域は、労働力不足にダイレクトに響くと思いました」
【クマール氏コメント】
「昭和の日本が好きなのですが、努力すればなんとかなるという価値観を持って、日本のいいところを残していきたいです。日本のいいところを経済的な形に変えていき、世界に貢献していくものにしたいと思っています」
SBIインベストメント賞
受賞:株式会社分子ロボット総合研究所

【加藤氏コメント】
「次世代の成長産業に投資させていただいています。株式会社分子ロボット総合研究所は研究段階としては非常に早い印象を持ちますが、1型糖尿病という大変な思いをしている患者さんに対しての研究開発をされていることに期待を込めました」
【小長谷氏コメント】
「基礎研究はいいところまでいっているのですが、社会実装にかなったものにするというところで、いろいろな方にご支援いただきました。これから頑張って本当に社会実装に進みたいと思います」
みずほ銀行賞
受賞:ENELL株式会社

【春原氏コメント】
「シンプルに子どもに話したいような会社。みずほ銀行はサステナブルと、グローバルに勝てるスタートアップ創出を掲げており、ENELL株式会社にはグローバルの目線があり、世界で勝てる会社になるのではないかと思いました」
【赤石氏コメント】
「水がないと人間は生きられない。我々の技術は、きれいな水を与えることで世界を健康にできるし、人間にとっての一番のベースになると思っています。世界で勝負できるようにお力を貸していただけたらと思います」
ANAホールディングス賞
受賞:株式会社フィールドワーカーズ

【津田氏コメント】
「まず、蚊へのパッションがすごい(笑)。ANAも、欧米だけでなくアジアのディべロッピングなところへの就航路線が増えてきました。蚊の問題は、渡航者の現地感染リスクのほか、飛行機に蚊を持ち込んで病原菌として日本に入る可能性もあり、エアラインとしても課題となっていますので、期待しています」
【星氏コメント】
「お話にあったように、国際線から日本に入ってくるリスクを踏まえると、蚊の問題は、アジア全体のプロテクションを日本から先導してやっていくことがまず必要だと思いました」
ジャフコ グループ賞
受賞:株式会社VISION IV

【沼田氏コメント】
「今朝、たまたまダイヤモンドの量子技術の話をしていました。ターゲットとしている市場も大きく、パワー半導体は日本が強い分野でもあり、日本初の技術で大きな成長や世界展開を期待できるかというところで、期待を込めて選ばせていただきました」
【小関氏コメント】
「ピッチコンテストで初めていただいた賞です。当初は量子の世界は視野に入れられていなかったのですが、量子センサー用にダイヤモンド基板を専門の先生にご評価いただいております。センサー向けのダイヤモンド基板で高純度な評価をいただきつつあるので、量子センサーとしても応用が可能と思いました」
各受賞者には、それぞれ副賞として、1on1での事業相談権が贈られます。
オーディエンス賞
受賞:株式会社KAMAMESHI

【石井氏コメント】
「オーディエンス賞は、会場及びインターネット視聴での参加者投票で選出されました。製造業が良くなることは、この国の産業が良くなることにつながるということなので、素晴らしい会社を賞として選んでいただいたと思います」
【小林氏コメント】
「起業から1年半でまだ何も成し遂げていませんが、今の時点でも事業ができていることに感謝し、明日からまた気を引き締めて、しっかり製造業の現場に足を運んで課題解決に向けて頑張りたいと思います」
オーディエンス賞には副賞として、独立行政法人 中小企業基盤整備機構 創業・ベンチャー支援部長が受賞者のお話をお伺いして、公的支援全般のサポートを実施する「追加支援パッケージ」が贈られました。
最後に、独立行政法人 中小企業基盤整備機構 創業・ベンチャー支援部 部長 石井芳明氏から、閉会の挨拶がありました。

「今回も100社を超える会社から応募があった中で19社を選ばせていただき、支援に当たりました。これから先、現実のものとして社会課題に貢献するという、もう一歩を進んでいただきたいと思います。中小企業基盤整備機構にも、このほかにいろいろな支援策があります。政府挙げての支援を最大限活用し、スタートアップエコシステムを盛り上げ、社会課題と経済成長を実現する、そういう日本になるようご尽力いただければと思います」
閉会後には交流会が開かれ、登壇企業が製品などと共にブースに立ちました。VC、金融機関、関連する企業、その他スタートアップにご関心ある方々と、直接質疑応答をしたり、情報交換、名刺交換したりするなど、活発なやり取りがなされ、大盛況のうちに幕を閉じました。